徹底した市民目線で
三つの柱を実践します
1.防災の視点からの仕組み
- 地区防災計画の策定
- 防災DXで防災情報の共有と管理
- 防災機能を持った公園の整備
- 住民主導型の避難所の開所及び運営
- 集会所への再生可能エネルギーの導入
- 消防団事務を市長部局に移管
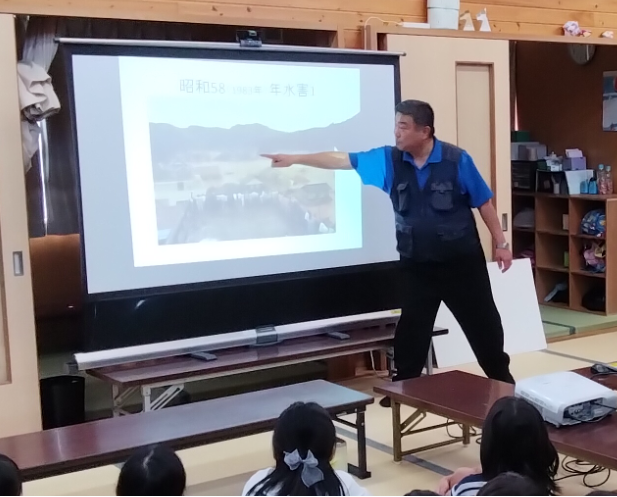
2.地域資源を活かした仕組み
- スポーツ施設を活かした合宿誘致
- 屋外競技場の水はけ等、発電所の石炭灰を活かした施設の整備
- 西条柿、石州和紙及び日本酒造を活かした産業振興
- リハビリテーションカレッジ島根を活かした地域の課題解決
- 渚の交番及びB&G海洋センターを活かした体験学習の充実

防災の視点で
3.中山間地域の郷土を守り抜く仕組み
~ やります「行政とのパイプ役を」 ~
- 農林水産従業者の後継者不足の解消への挑戦。
中山間地域では農林水産業の後継者不足が深刻な問題です。若者へのアピールや支援制度の充実を通じて、新たな担い手を確保し、地域の基幹産業を支える取り組みを進めます。 - 耕地の荒廃と休耕田の対策への挑戦。
耕地の荒廃と休耕田の増加は、地域の景観や生態系に悪影響を与えます。耕作放棄地の有効活用や土壌改良の支援を行い、地域の農業の持続可能性を高めます。 - 通院、買い物など移動手段の確保への挑戦。
高齢化や人口減少に伴い、通院や買い物などの移動手段が不足しています。公共交通機関の整備やコミュニティバスの導入、タクシー料金の助成など、移動手段の確保に向けた対策を講じます。 - 他地域に住んでいる家族との連絡手段の情報基盤の構築への挑戦。
中山間地域に住む高齢者などが他地域に住む家族と連絡を取るための情報基盤が必要です。インターネット環境の整備やスマートフォンの活用支援を通じて、家族間の連絡手段を強化します。 - 地域自治活動における介護、福祉、医療対策・連携への挑戦。
地域の高齢者や弱者を支えるため、介護・福祉・医療の対策と連携を強化します。地域内での医療機関や介護サービスの連携を深め、住民が安心して暮らせる環境を整えます。 - 郷土を守り抜くには、市街地の発展は不可欠であり、地元産業の発展への挑戦。
郷土を守るためには市街地の発展が重要です。地元産業の振興や新たなビジネスの創出を支援し、地域経済の活性化を図ります。

4.生涯学習を活かした仕組み
- スポーツ施設を活かした合宿誘致
- 屋外競技場の水はけ等、発電所の石炭灰を活かした施設の整備
- 西条柿、石州和紙及び日本酒造を活かした産業振興
- リハビリテーションカレッジ島根を活かした地域の課題解決
- 渚の交番及びB&G海洋センターを活かした体験学習の充実

防災の視点で
3.地域医療・福祉と連携した仕組み
~ やります「行政とのパイプ役を」 ~
- 農林水産従業者の後継者不足の解消への挑戦。
中山間地域では農林水産業の後継者不足が深刻な問題です。若者へのアピールや支援制度の充実を通じて、新たな担い手を確保し、地域の基幹産業を支える取り組みを進めます。 - 耕地の荒廃と休耕田の対策への挑戦。
耕地の荒廃と休耕田の増加は、地域の景観や生態系に悪影響を与えます。耕作放棄地の有効活用や土壌改良の支援を行い、地域の農業の持続可能性を高めます。 - 通院、買い物など移動手段の確保への挑戦。
高齢化や人口減少に伴い、通院や買い物などの移動手段が不足しています。公共交通機関の整備やコミュニティバスの導入、タクシー料金の助成など、移動手段の確保に向けた対策を講じます。 - 他地域に住んでいる家族との連絡手段の情報基盤の構築への挑戦。
中山間地域に住む高齢者などが他地域に住む家族と連絡を取るための情報基盤が必要です。インターネット環境の整備やスマートフォンの活用支援を通じて、家族間の連絡手段を強化します。 - 地域自治活動における介護、福祉、医療対策・連携への挑戦。
地域の高齢者や弱者を支えるため、介護・福祉・医療の対策と連携を強化します。地域内での医療機関や介護サービスの連携を深め、住民が安心して暮らせる環境を整えます。 - 郷土を守り抜くには、市街地の発展は不可欠であり、地元産業の発展への挑戦。
郷土を守るためには市街地の発展が重要です。地元産業の振興や新たなビジネスの創出を支援し、地域経済の活性化を図ります。

